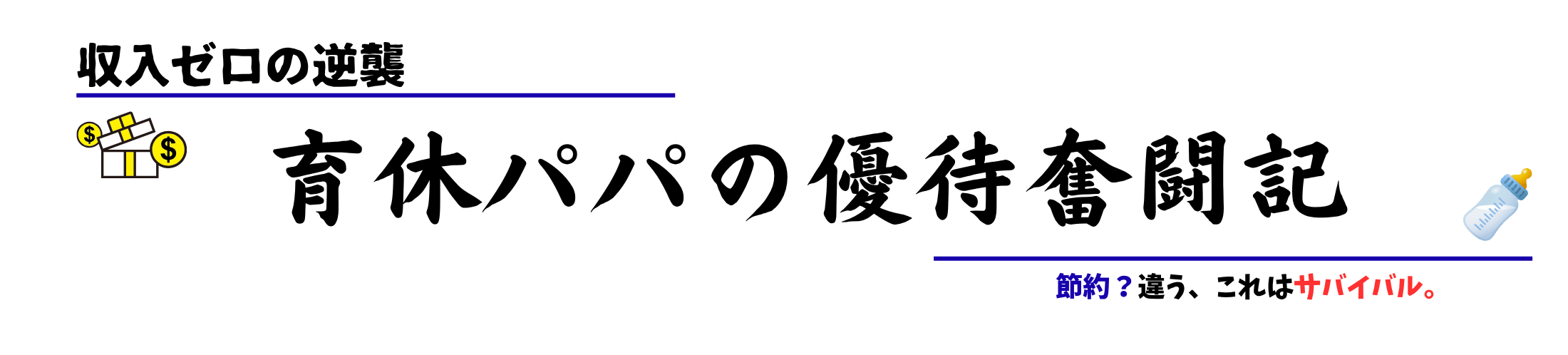はじめに
「育休、取れるのが当たり前になってきたよね」——そんな言葉を耳にすることも増えてきました。確かに法律も整備されてきて、男性育休の取得率も少しずつ上がっています。
でも、現実はどうでしょうか?
「取れる人は取れるけど、取れない人はずっと取れない」——そんな“育休格差”が、いま静かに社会の中で広がっています。
1. そもそも「育休を取れる環境」ってどんなもの?
- 雇用保険に入っていること
- 同じ会社に1年以上継続して勤務していること
- 子どもが1歳(または最長2歳)になるまでの間に育児する意思があること
さらに、“取得しやすい職場環境”という見えない壁も存在します。
たとえば大企業では「育休=当然」という空気感がありますが、中小企業や個人経営の現場では、「抜けられると仕事が回らない」「代替がいない」など、“制度はあるけど実質ムリ”な空気があるのです。
2. 給付金の落とし穴:「生活できる人」と「できない人」
育児休業給付金は「休んでも収入がゼロにならない」ための制度ですが、支給額には明確な上限があります。
- 最初の180日間(67%):月額上限は約315,369円
- 181日目以降(50%):月額上限は約235,350円
この上限に達するのは、月収が約47万円を超える人です。
つまり、高年収の人にとっては、育休を取ることで手取りが大幅に減る可能性があります。
そして皮肉なことに、そういった高収入の人たちは以下のようなライフスタイルを持っている場合も多く、「休むくらいなら働いたほうが家計的に楽」という判断になることも少なくありません:
- 立派な家に住んでいる
- 高級車に乗っている
- 外食やレジャーなどの出費が多い
一方で、もっと深刻なのは中間層以下の家庭です。
- 今の給料でも貯蓄ができず、カツカツの赤字家計
- 生活費や住宅ローンの返済でいっぱいで、休む余裕がない
制度はあっても、生活がすでにギリギリなら、選択肢にすら入れられない。育休を“取得できる人”と“取得できない人”の差は、収入ではなく余力の有無なのかもしれません。
3. 制度が届かない人たち
本来、もっとも制度が届いてほしいのは、ここにいる人たちです。
- 非正規雇用で育休の条件を満たせない人
- 妊娠中に退職を余儀なくされた人(「おめでた退職」など、制度を使わせない空気の中で自ら辞める形に追い込まれている)
- 自営業やフリーランスで、育休制度の対象外となっている人
「余力がある・ない」以前に、そもそも制度そのものに手が届かない人たちがいます。
妊娠中に職場を離れる——本来であれば守られるべき状況なのに、空気を察して辞めざるを得ないのは、実質的な圧力とも言えます。制度を利用させない会社の姿勢は、雇用の自由を超えて問題です。
また、自営業・フリーランスなどの働き方をしている人たち。全てが自由で良いように見えても、収入が途絶えれば即生活困難に陥る人も多くいます。
こうした“制度の網”から漏れた人々に対して、私たちの社会はまだ十分に手を差し伸べられていないのが現実です。
制度がある=すべての人に届いているわけではない。 その事実を、もっと多くの人が知るべきだと感じています。
4. 僕が育休を取れた理由、そして感じた違和感
僕が「育休、1年間取ります」と話したとき、真正面から「いいじゃん!応援するよ!」と言ってくれたのはほんの数人。親しい友人や、心から信頼している人たちだけでした。
それ以外の多くは、戸惑った表情や気まずそうな反応で、まだまだ“特別な存在”として見られているのを感じました。
でも夫婦の中では、この育休は前向きな選択でした。制度が拡充されたタイミングで「次に子どもができたら育児に向き合おう」と話し合い、授かりが分かったときに「じゃあ1年取ろう」と自然に決まった育休でした。
会社では外部講師による育休セミナーもありました。内容は有意義で、家族との向き合い方や職場サポートの重要性、障害児を育てる話なども共有され、育休の現実に触れる良い機会でした。
ただ、どこか“啓蒙的”なトーンもあり、「産後の恨みは一生」などの表現に違和感も感じました。きっとこれは、過去に関わらなかった父親像への警鐘かもしれませんが、「取らないと恨まれる」という脅しに聞こえてしまったのです。
育休って、本来は脅して取らせるものじゃない。 もっと「家族と向き合えるからいいよ」「こんな経験ができるよ」と前向きに伝えられる空気が広がってほしいと感じました。
5. 「育休が取れること」は、当たり前ではない
出生率が落ち、新生児の数も減っている今の日本。
その背景には、経済的な理由だけでなく、人との関係性やプロセスが薄れてきている現実があります。
AIの登場で、こうして自分の思考を整理できるようになったけど、それと引き換えに「人と関わること」が減ってきている。
- 恋愛しなくてもいい
- 結婚はコスパが悪い
- 子どもは負担だ
そう思う人が増えるのも仕方ないかもしれません。
でも僕は、そこに違和感を持ち続けたい。
育児は「損」じゃない。 辛くて、苦しくて、どうしようもない時もあるけれど、それでも「可愛い」「愛してる」と思える瞬間がある。
この感情こそ、人間にしかない、かけがえのない本当の価値なんだと思います。
育休を取る人が増えるだけじゃなく、育児そのものがもっと尊重される社会になるように。
「子どもを育てることの価値」を、もう一度みんなで考えていけたらと思っています。
おわりに
育児は「個人の努力」で乗り切るものではなく、「社会」で支えるべきもの。育児休業制度は、その入口です。
制度が届いていない人にこそ、ちゃんと届くように——そんな願いを込めて、この記事を書きました。