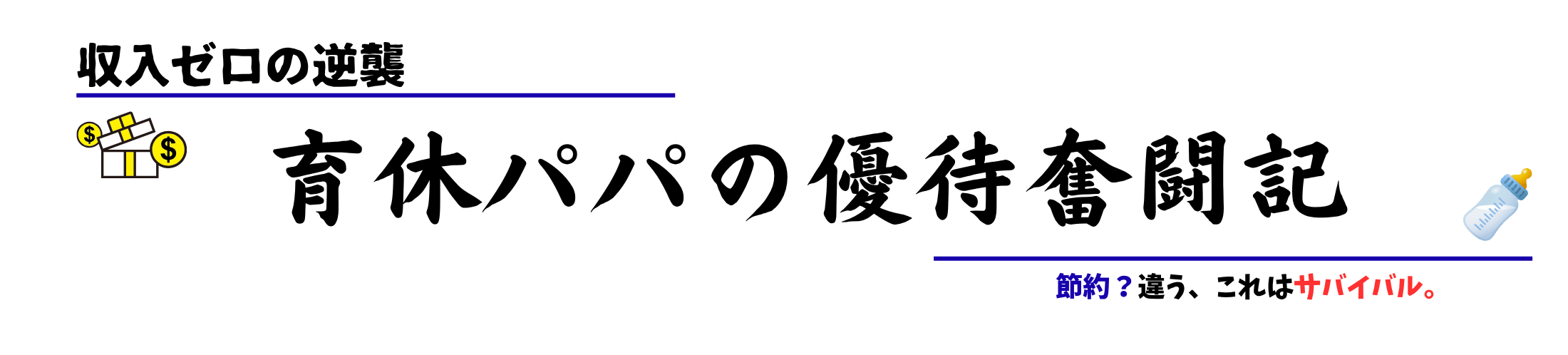先月、息子の5歳児健診に付き添った。
場所は地域の健康支援センター。
平日の昼間、来ていたのは当然ながら、ほとんどママだった。
というか、体感で言えば8〜9割がママ。
パパは僕含めて、ほんの数人。もしかしたら1人か2人かもしれない。
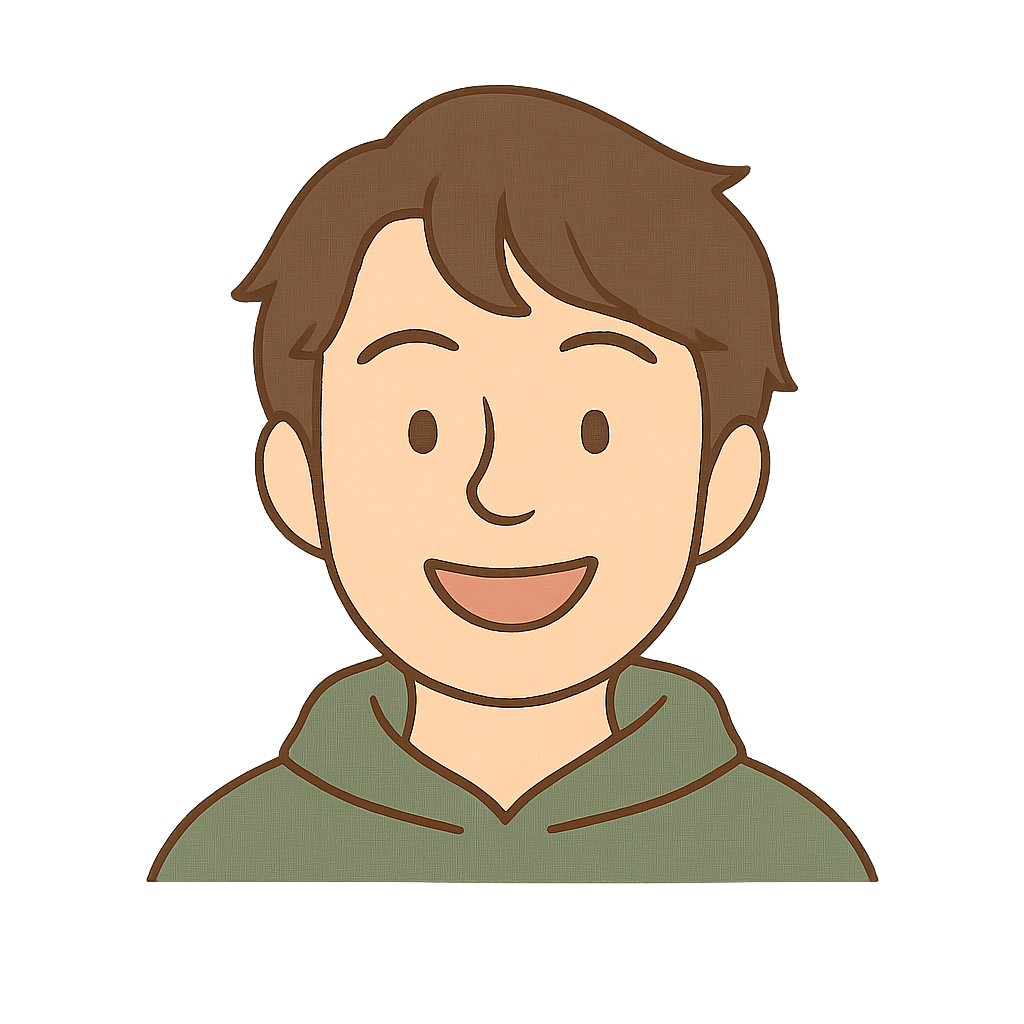
「あ〜、やっぱりここはママの世界だな…」
そんなことを思いながら、番号札を握りしめて順番を待っていた。
コミュ力が高ければ輪に入れるのかもしれないけど、
あいにく僕はコミュ障系育休パパ。
無言で呼ばれるのを待つだけで精一杯だった。
健診の流れの途中で、ある保健師さんに呼ばれて言われたひと言。
「あれ?今日はママはどうしたんですか?」
とても自然な、何気ないひと言だった。
その時は「またか〜」と思いつつ、
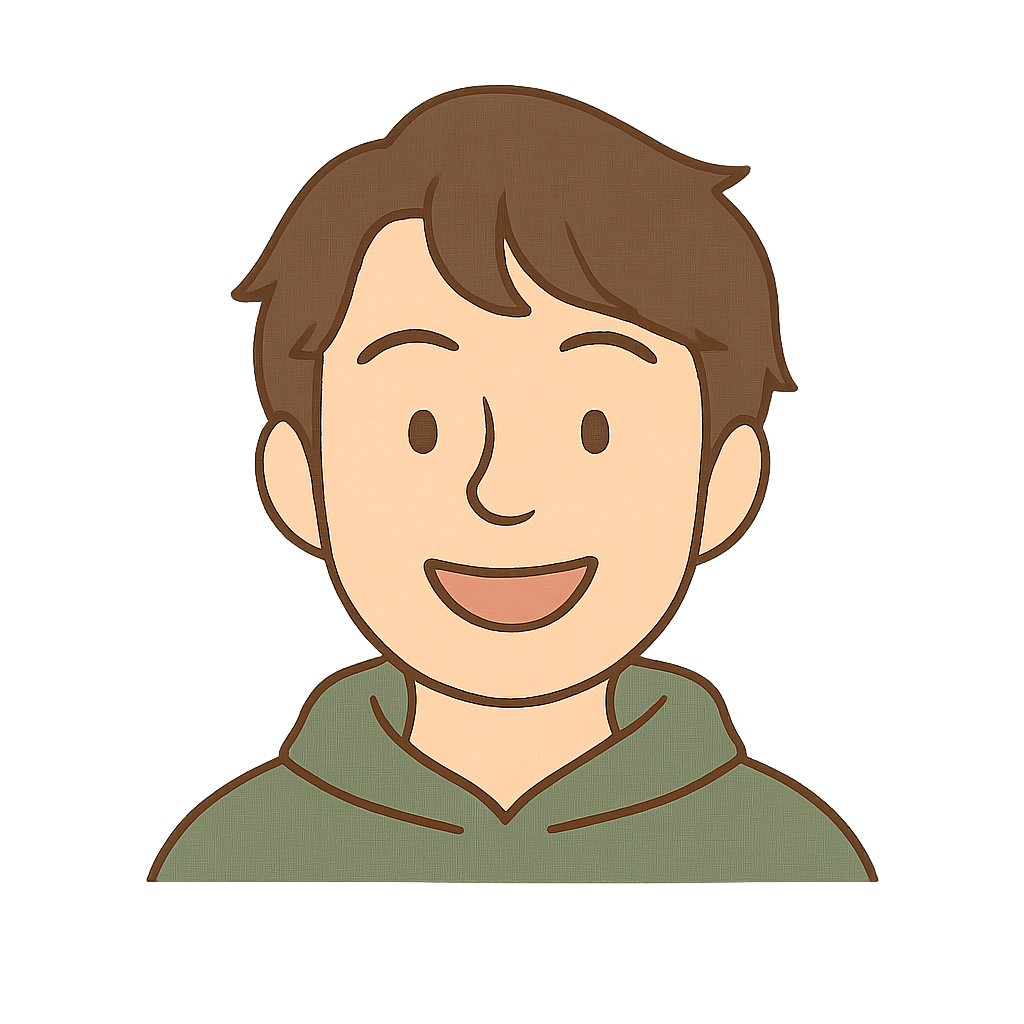
「実は今、育休中でして…赤ちゃんと一緒に自宅です」
って、いつものように説明した。
説明すれば、たいてい「えらいですね〜」とか「素敵なお父さんですね」と返ってくる。
ありがたい言葉だ。
でも、どこか虚しさが残る。
だって、ママが来てたら何も言われない。
それが“普通”だから。
パパが来たときだけ、「すごい」って言われるのは、
まだ社会では“パパが育児する”ことが例外扱いなんだっていう証拠みたいに思えてくる。
そして今日。
そのときの保健師さんが、産後訪問で我が家に来てくれた。
「先月は5歳児健診でありがとうございました〜」
お互いに軽く挨拶しながら、
あ、やっぱり覚えられてたのかとちょっとだけ納得した。
僕があの場にいたのは、きっと珍しかったんだろう。
ママばかりの中で、パパが育児の最前線にいる姿って、
まだまだ目立つ存在なんだと思う。
でも正直、目立ちたいわけじゃない。
特別扱いされたいわけでもない。
できればもっと、
「育児する父親」が空気みたいな存在になってほしい。
いてもいなくても驚かれない、そんな存在に。
ただ、やっぱり現実は違う。
赤ちゃんの安心感も、子どもの変化への反応も、
やっぱりママの方が的確で、“当たる”ことが多い。
それが“経験値”なのか“本能”なのかはわからないけど、
父親である自分には、届かない場所がある気がする。
「私ばかりが大変」
そう言われたとき、
こっちの中にはいつも、“言えない気持ち”がある。
「こっちだって、考えてる」
「ちゃんと向き合ってるつもりなんだけどな」
「でも、なんかズレてるんだよな」
育児って、“母親の土俵”なんだなって思うことがある。
パパはその外側から、
「えらいね」とか「助かってるよ」と言われながら、
どこか蚊帳の外に立たされてるような気がする。
家庭の中でも、社会の中でも、
父親の考えって“サブ的なもの”として扱われやすい。
年収の話になると「男の方が多い方がいい」とか言われるけど、
子どもに対する考え方とか、育児方針については、
あまり聞かれないし、通らない。
今、育休中の僕は──
進んでいるのか、立ち止まっているのか、
もしかしたら、後退しているのかもしれない。
でも、そんなふうに悩んでいることすら、
ちゃんと声に出せていない。
だから、こうして書いておこうと思う。
大きな出来事じゃない。
ただの、健診と産後訪問のあいだに起きた、ちょっとしたこと。
でも、
“ちょっとしたこと”の積み重ねが、
父親の育児というものの現在地を表しているような気がするから。
この距離感が埋まるには、きっとまだ時間がかかる。
それでも僕は今日も、赤ちゃんと、5歳児と、一緒にいる。
この毎日が、自分なりの育児の形だと信じて。